vol.04
すべてを出し切ったフランス本選。
チームJAPANの挑戦はこれからも続く
2025.03.31
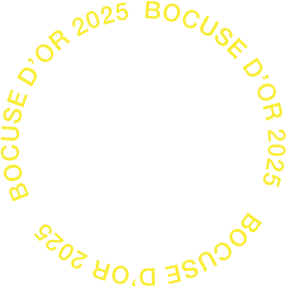

1月26日(日)、27日(月)の2日間にわたり、フランス・リヨンで「ボキューズ・ドール国際料理コンクール2025 フランス本選」が開催された。世界各国から24の代表チームが参加し、貝沼竜弥(かいぬま りゅうや)率いるチームJAPANは、11位の結果となった。今回は、フランス本選の様子をレポートするとともに、日本代表としての挑戦を終えた貝沼に改めて話を聞いた。
INDEX
フランス料理のトップシェフを決める戦いがついに始まった

フランス本選は「シラ外食産業見本市」内にある特設会場で行われた。スタジアムのような大きな会場には、前方ステージに12のキッチンが設置され、観客席では各国の応援団が歌や鳴り物で声援を送るなど、お祭りのような熱気に溢れていた。
世界70か国から厳しい予選を勝ち抜いた24の代表チームが、5時間半という限られた時間の中でプラッター(大皿料理)とプレート(皿盛り料理)の2つのテーマで料理を仕上げていく。審査員も出場する24か国から選出され、料理の味や仕上がりに加えて、調理中の衛生管理や食材を無駄なく使っているかなども厳しくチェックし、総合点で順位が決定する。
日本は大会2日目の2番手としてスタート。5時間半にわたる戦いが、ついに始まった。
トラブルにも慌てることなく、制限時間内に料理が完成

フランス本選のプレート(皿盛り料理)のテーマは、セロリアック(根セロリ)と葉付きセロリを主役とした一皿で、ストーンバス(ニベ)とロブスターを組み合わせた温菜と温製のサバイヨンソースを添えることが求められた。本大会からプレートも大皿に盛り付けるという新ルールが導入され、より制限時間内に仕上げるハードルが高まるなか、貝沼率いるチームJAPANは美しいプレートを完成させた。

実は想定外のトラブルが多発し、その都度調整しながら進めなければならなかったというが、プレートは大きな変更なく完成させることができた。その結果、プレートでは今大会で2位に入賞したデンマークを超える787点の高得点をマーク。審査員から高い評価を得ることができた。

プラッター(大皿料理)の課題食材は、鹿肉、フォアグラを使ったパイ包み焼きで、お茶を使ったコンソメを添えることが求められた。株式会社カナリアの徳田祐司(とくだ ゆうじ)氏がデザインした大皿に美しく盛り付けられ、多様な素材の風味や食感を見事に調和させた料理に仕上がった。

しかし味の評価は高かったものの、パイ包み焼きのルールの解釈の違いにより、50点の減点を受けてしまった。これまでの傾向ではルールの拡大解釈をしてもさほど大きな問題にはならなかったのだが、今大会は例年以上にレギュレーションの徹底が求められた。改めて、ボキューズ・ドールを勝ち抜くには、事前の情報収集や戦略の組み立てが重要であることが明確になった。
日本代表として走り抜けた1年半は、貴重な財産になった

フランス本選を終えた貝沼に、改めて今回の大会を振り返ってもらった。
「世界大会という大きな舞台でしたが、緊張することなく、落ち着いて臨むことができました。想定外のトラブルが多く、思うようにいかなかった部分もありますが、できることはすべて出し切れたと思います」。
「この1年半、会社や店舗の垣根を超えて本当に多くのシェフや関係者のみなさんにサポートいただいたおかげで、最後まで走り抜くことができました。日本代表として過ごした日々は、葛藤もありましたが多くの学びがあり、間違いなく自分の料理人生において貴重な財産になりました。大会を終えて改めて、“食材と真摯に向き合い美味しい料理を作る”、という日々の積み重ねが重要だと実感しています」。

「フランス本選が終わった直後は“やっと終わった……”という気持ちが強く、もう挑戦することはないと考えていましたが、しばらく経った今は、いつかまた代表になれるチャンスがあったら、とふと考えることもあります。ただ、当面は料理長になることを目指して、その準備をしていきたいので、料理長になれた時にまた改めて考えたいですね」。
2027年大会に向けて、チームJAPANの挑戦は続く

今回、日本代表をサポートする体制を整えチームJAPANとして挑んだが、強豪国と対等に戦っていくには、まだ多くの課題が残る。本大会でチームJAPANのテクニカルディレクターを務めた「HAJIME」のオーナーシェフ米田肇(よねだ はじめ)氏は、3月に行われた報告会で「今後はレギュレーションの徹底理解と戦略的な準備が必要」と語り、国として戦略的にボキューズ・ドールに挑む強固な組織づくりの重要性を改めて訴えた。
次回大会(第21回)は2年後の2027年。日本代表は、今回チームJAPANでコーチとして参加した浅野哲也(あさの てつや)シェフだ。浅野シェフは「HOTEL THE MITSUI KYOTO」にあるシグネチャーレストラン「都季(TOKI)」で料理長を務める。フランス本選の準備からチームに参加し得られた経験は、きっと次回大会に生かされるだろう。2027年大会に向けたチームJAPANの戦いは、すでに始まっている。
